暮らしを彩る出版社
コラム
児童期編その1「ルールを守ろうと思う子に育てていく」

小学校に入ると、親も子もドキドキ。幼稚園、保育所時代と大きく違うのは、教壇に立つ先生の方を見て、机に向かい、椅子に座ってのお勉強が始まることです。
少し前は、「小1プロブレム」と言われ、きちんと座っていられない生徒が多いことを問題視されていましたが、今はそうであることを想定しての教員の対応、授業の進め方ができてきたように思えます。それでも、授業中に歩き回る子がいることも事実です。
そういった児童だけに限らず、学校に行く上で、ルールがあるということを、親が子供に教えておくことが大切です。ルールは、あらゆる社会に存在します。
人は、社会と関わらずに生きていくことはできません。ルールを守ることができないと、周りに迷惑を掛けるだけではなく、自分も周りとなじめなかったり、扱いが違うと不満に思ったり、本人もしんどくなっていくのです。
ルールを守ることは、家庭教育で培われていく部分がとても大きいのです。「どうせ、学校で教えてくれるものなんだから、学校に任せればいい」ことではありません。ルールを守るのは、〈そうしよう〉と思えるかどうかの感覚です。
例えば「授業中に立ち歩くのは、先生がおもしろくない授業をしてるからでしょう?」と言ったら、それは「座っておかないといけないルールがあり、それを守ろうね」ということを子供に教えようとしていないことになります。
〈みんなが守っているルールをできるようになろうね〉という思いは、親が教えていくことなのです。小学校に入る前から、「お約束ね」と、決まり事を実行させていくことはしていると思いますが、家庭内ではなく、社会でのルールが多くなる始まりが小学校なのです。
学校は教育の場ですから、今はできなくても待ってくれる機関であり、期間です。うちの子ができないのは、先生が、学校が、とクレームを言うだけの親であっては、結局、我が子を成長させられません。
その子なりに、ルールを守れる力を育てていくのが、〝親力〟なのです。
『芸生新聞』2019年4月1日付掲載



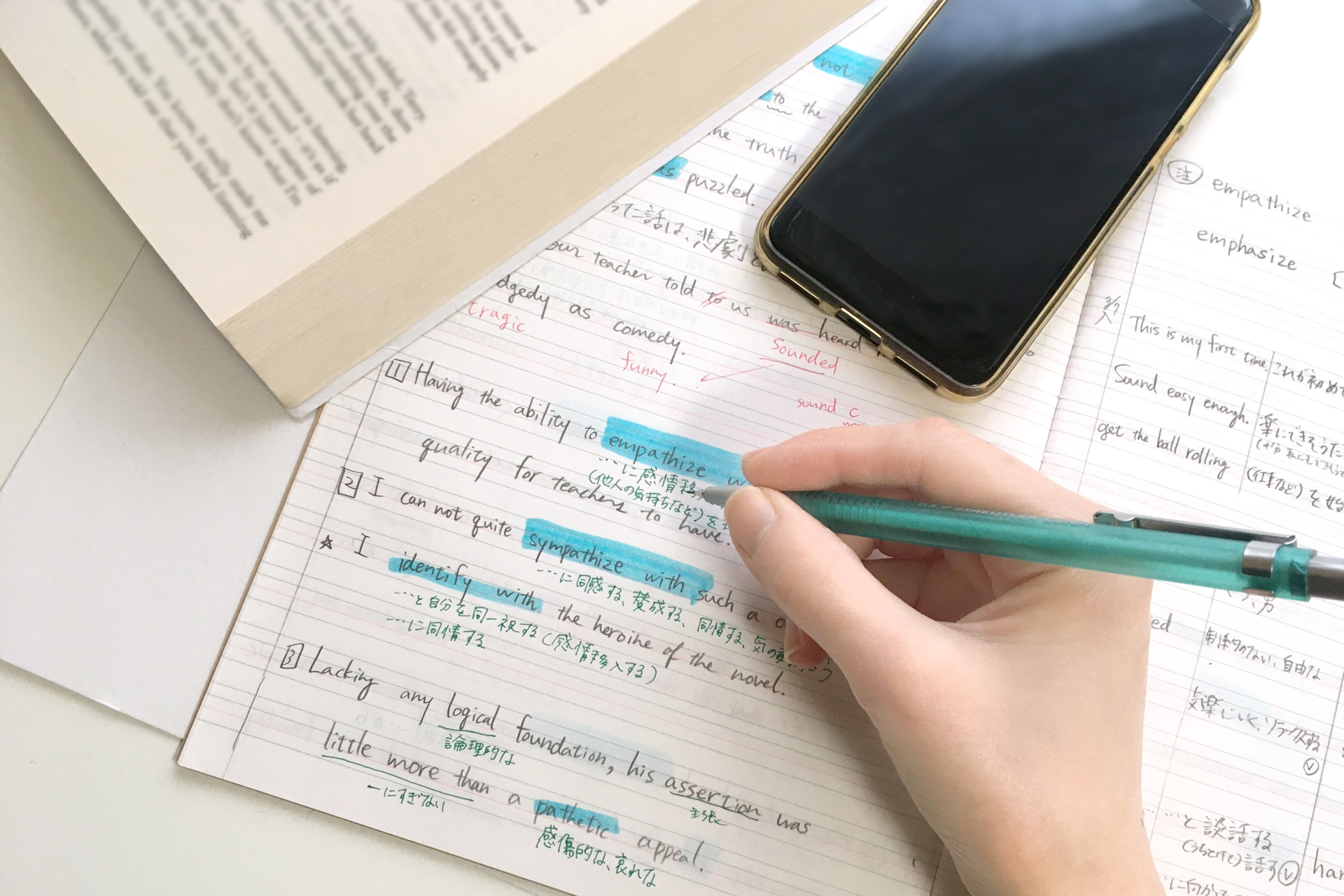

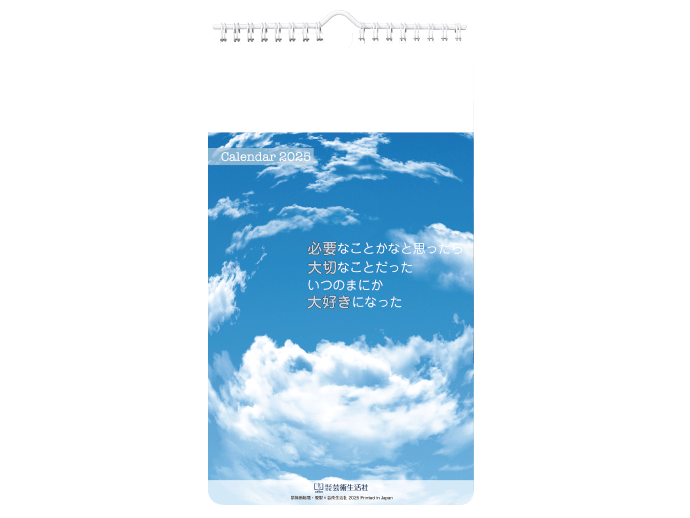

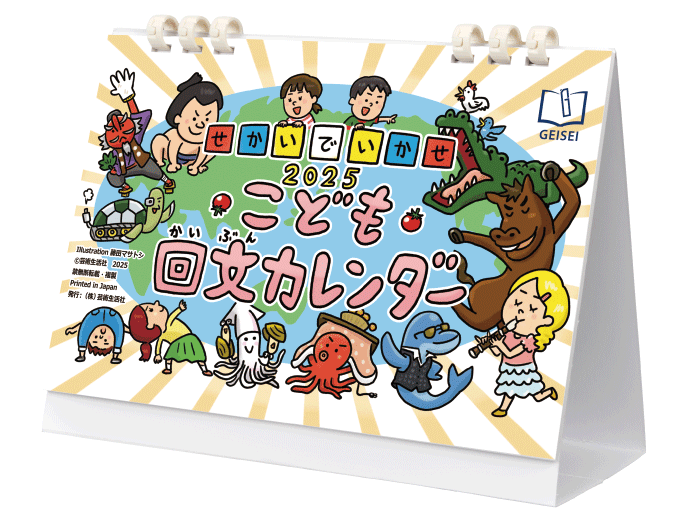
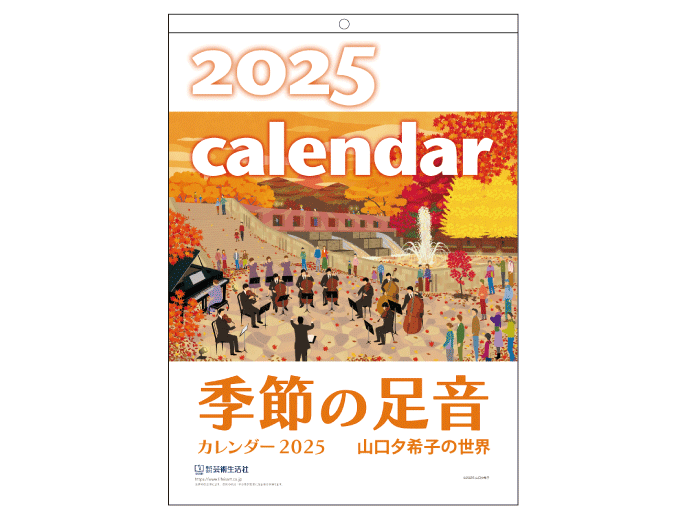
臨床心理士の考える子育てのヒント
1998年から中学校のスクールカウンセラーを始め、現在、兵庫県内の小・中・高で生徒、教師、親の相談を受けている。こころの悩み相談「コミュニケーションズサポート」代表。PL学園高等学校卒業。
川嵜由起美(かわさきゆきみ)臨床心理士・公認心理師