暮らしを彩る出版社
コラム
思春期編その14「情報をうのみにせずに自ら判断を」

口を利いてくれない、部屋にこもることが増えた、学校で何かあったようだ……。悩み多き思春期、反抗期に入ると、子供の様子が今までと変わってきて、親が戸惑うことも。それまで優等生タイプだった真面目なお子さんだと、なおさらでしょう。
それをインターネットで調べて、〈うつになったのでは?〉〈心の病気じゃないか?〉と、心配し過ぎてしまう親御さんが増えました。不安になって更に調べると、どんどん心配の種が見つかる〝負のループ〟に陥り、しまいには不安のドツボにはまってしまう。その上、子供が学校へ行かなくなると、ますます不安は増していきます。
◇
今の風潮では、子供に無理をさせてはいけない、つらいことから解放してあげないといけないという考え方が主流のようですが、果たしてそれが、どの子供にもどんな状況でも当てはまるのでしょうか。ネットに書いてあったから、周りからそう言われたから、〈わが子のことはそっとしておこう〉と考えていませんか?
身近なママ友に話して「それは無理させなくていいわよ」などと同意を得て、1日ないし2日ほど様子を見て、疲れが取れるのを待つ。それはいいのですが、その後も〈そっとしてあげないと……〉と思い込んで、子供に働きかけられないのなら、それは親のアンテナの問題です。
◇
〈このままでいいのかな?〉と気になりながらも、ネットの「そっとしておく」「無理強いしない」をうのみにして関わらないのは違います。
もし、あなたが仲の良いママ友から「うちの子、しばらく学校へ行けてないの」と相談されたら、「しばらく様子を見たら?」「無理させるのはよくないんじゃない?」と言いたくなりますよね? それは、その親御さんに対しての心遣いからの言葉で、その子のことが詳しく分からないので、当たり障りのない言い方になるのです。
ネットも同様で、あなたの子供のことが分かって書かれているわけではありません。わが子について怖がったり、不安に思ったりすることはありません。〈誰もが通る思春期の悩みなんだ〉と思えたのなら、笑い飛ばすくらいの判断ができる〝親力〟を付けてほしいのです。きちんとした診断を受ける必要があるかの判断は、それからです。
『芸生新聞』2022年12月5日付掲載



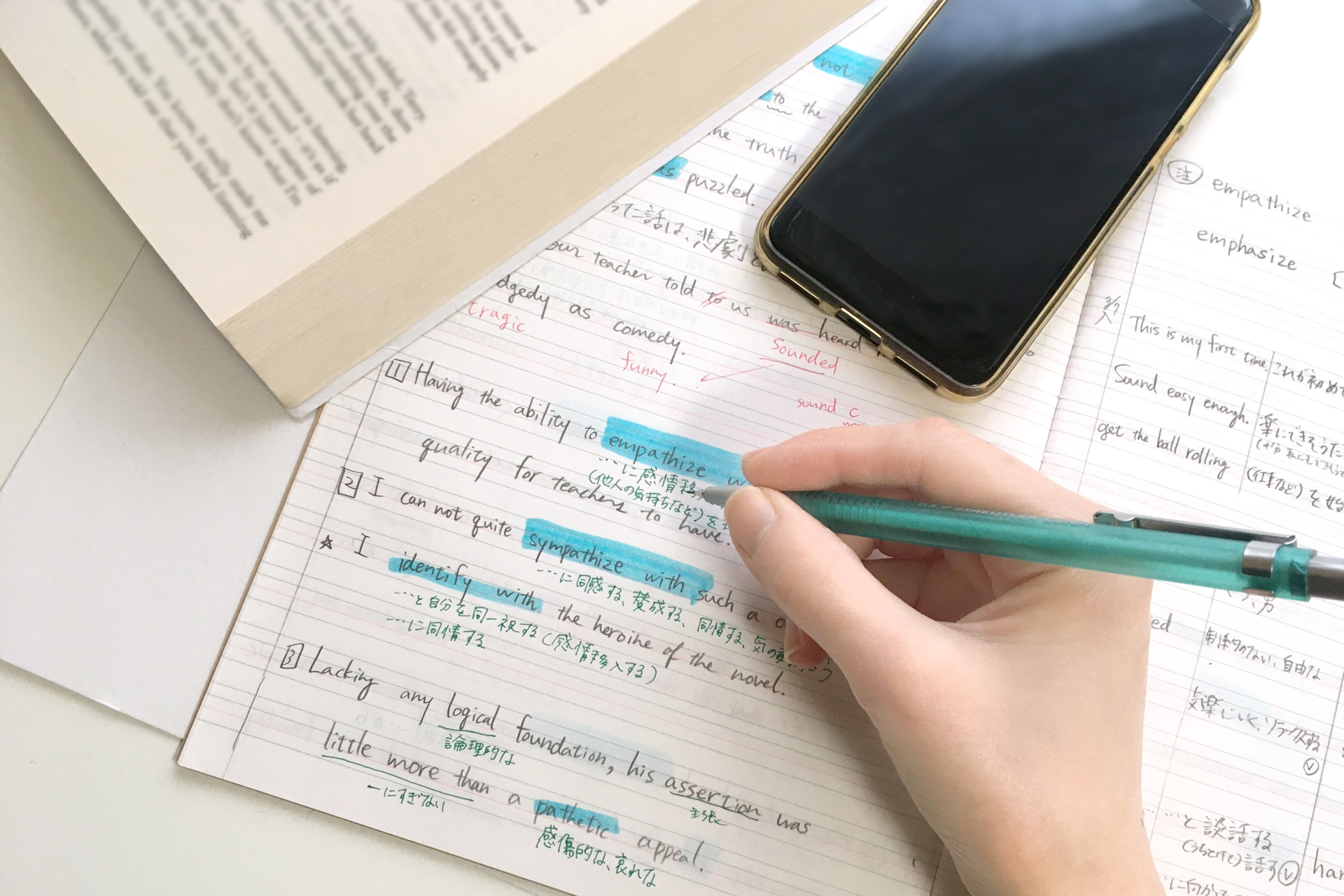

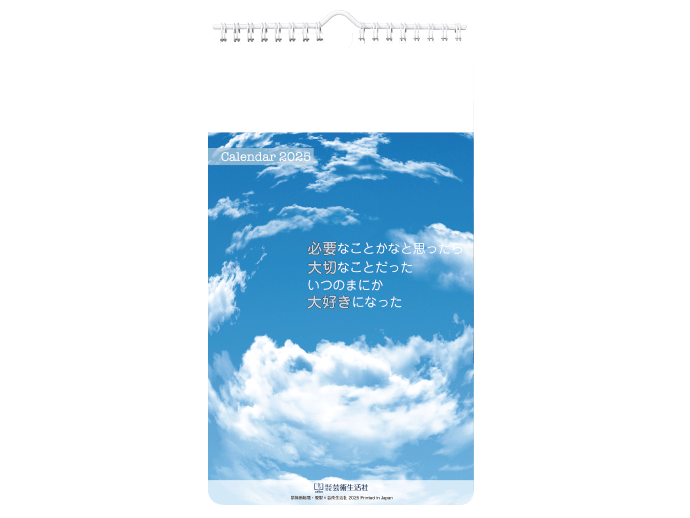

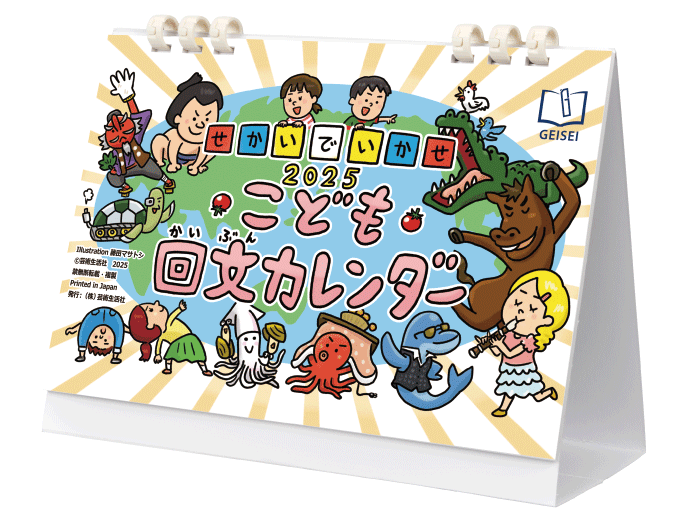
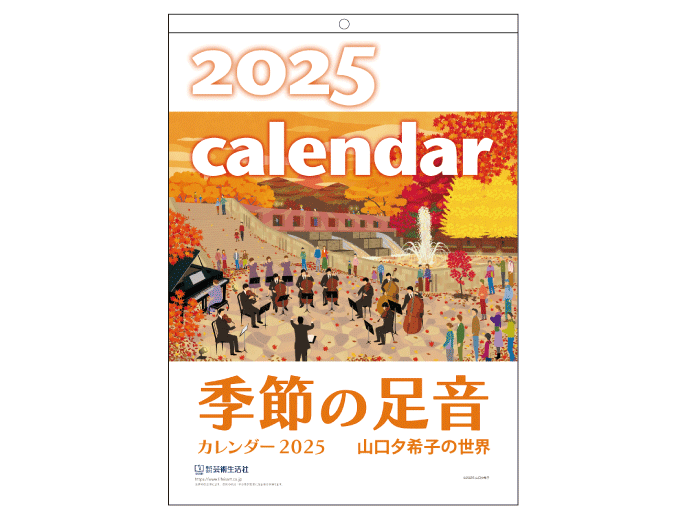
臨床心理士の考える子育てのヒント
1998年から中学校のスクールカウンセラーを始め、現在、兵庫県内の小・中・高で生徒、教師、親の相談を受けている。こころの悩み相談「コミュニケーションズサポート」代表。PL学園高等学校卒業。
川嵜由起美(かわさきゆきみ)臨床心理士・公認心理師