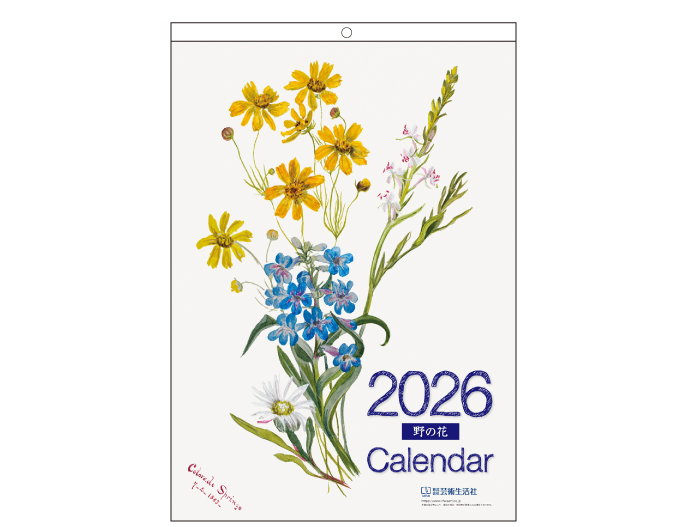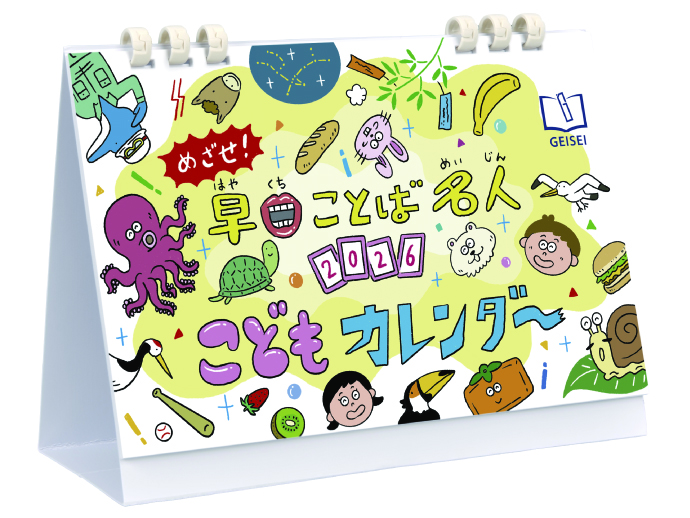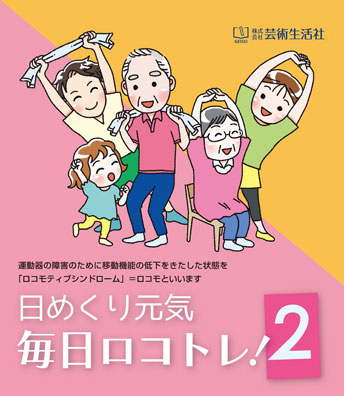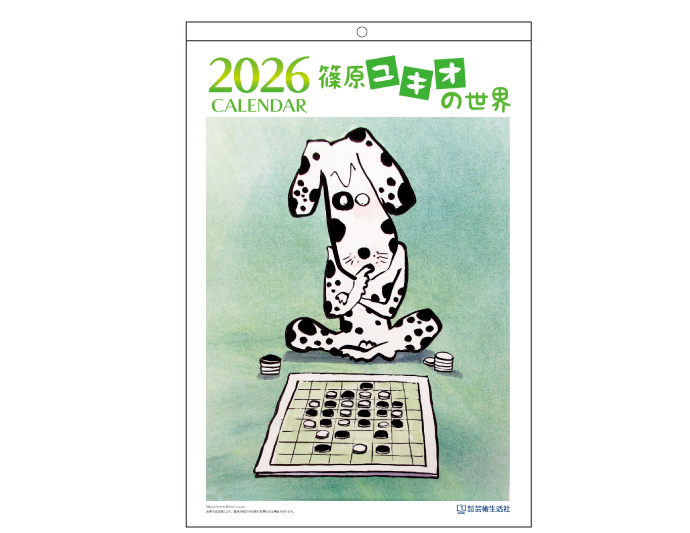昨年の終わりから、恐ろしい新型コロナウイルスの流行が、全世界を震撼させています。先進国で多くの死者を出し、医療危機、医療崩壊といわれる状況が現実のものとなり、「家から出ないでください。学校も休校、職場もテレワーク・リモートワークをしてください」という事態になりました。
阪神・淡路大震災や東日本大震災、各地であった地震や台風災害を経験している大人でも、こんなことが起こるなんて、と未曽有の出…… 続きを読む
暮らしを彩る出版社
コラム
- TOP
- コラム
-
親子コミュニケーション
特別編「子供を育てる皆さんへ」
-
親子コミュニケーション
児童期編その9「宿題は習慣付けることが大切」
小学校に入ると、お勉強が始まり、宿題が出るようになります。初めのうちは、ゆっくりのペースでなじむように考えられていますし、宿題の量も、そう多くはないことが多いでしょうから、きちんと宿題を済ませることができます。 本来、子供は好奇心のかたまりですから、知識欲にあふれ、勉強、宿題を頑張る気持ち満々です。ママが「宿題したの?」と聞く前に、「もう済ませた!」なんてことが、初めのうちはよくあるでし…… 続きを読む -
親子コミュニケーション
児童期編その8「親が心配すると、子供も心配ばかりする」
登校する時は、近所の高学年のお兄さんやお姉さんたちと一緒に集団登校し、下校はパラパラで、低学年でも、数人や1人で帰ってくる地域もあるでしょう。 1年生で、入ったばかりの時は、心配に思うママもいるでしょうが、急な飛び出しをしないことや信号を守ることなど、基本的な通学のルールができるなら、過剰な心配はやめましょう。 親が心配していると、子供も心配ばかりする子になります。心配ばかりする…… 続きを読む -
親子コミュニケーション
児童期編その7「食べ物に感謝する心を大切に」
小学校に入ると、毎日、給食があります。幼稚園や保育園のころから経験しているでしょうが、給食当番がいて、用意をして配膳する一連の作業も生徒がするようになるのが大きく違いますね。 一昔前とは違って、全部食べるまで残される、とかは無くなったでしょうから、今は給食がいやでたまらない子も減ったかもしれません。 きちんと栄養やカロリーを計算され、メニューを工夫して作られているのですから、感謝…… 続きを読む -
親子コミュニケーション
児童期編その6「担任の先生の良い所を見付けて」
学校に行き始め、ママ友と担任の先生の話をすることがあるでしょう。いろんな子供がいるように、先生方も、いろんな個性を持っているはず。 そこで、〈教員と我が子の相性が合わないかも〉と思うこともあるでしょう。だからといって、「先生が外れた」と言ったりすることはやめましょう。クジではないのですから、当たり外れでは判断できないですよね。 どんな人間でも、長所と短所があって当たり前、教師だか…… 続きを読む